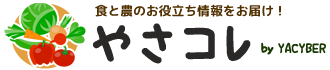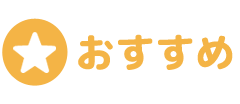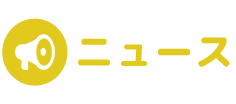今回は、天下の台所・大阪を支えてきた、「なにわの伝統野菜」についてご紹介します。
大阪は古くから食文化が栄え、それを支える野菜も独自のものが多く存在しました。
しかし戦後になると、生産性向上のための品種改良や農地の宅地化、食習慣の変化によって、地域独自の野菜が姿を消していきました。
「なにわの伝統野菜」とは
そんななか、近年再びそういった伝統野菜を見なおそうと、大阪府や関係機関が「なにわの伝統野菜」の発掘と復活に力を入れています。
種や栽培方法を守ってきた農業者と連携し、現在、17品目の野菜が「なにわの伝統野菜」の認証を受けています。
認証の基準は
- 概ね100年前から大阪府内で栽培されてきた野菜
- 苗、種子等の来歴が明らかで、大阪独自の品目、品種であり、栽培に供する苗、種子等の確保が可能な野菜
- <府内で生産されている野菜
の3つで、各地域で活発に伝統野菜のPRにも取り組まれ始めました。
「なにわの伝統野菜」の一部をご紹介
毛馬胡瓜(けまきゅうり)
江戸時代末期から大阪市都島区周辺で栽培されてきた毛馬胡瓜は、昭和初期頃にはほとんど生産されなくなり、幻の野菜となっていました。しかし平成10年に当時の大阪府農林技術センターが復活に成功、いまでは普及活動が活発に行われています。
上部三分の一が緑色で、残りは薄緑~白色をしているのが特徴です。水分は少なめで、パリッとした食感は漬物に適しています。
玉造黒門越瓜(たまつくりくろもんしろうり)
大坂城の玉造門が黒塗りだったことから、この玉造付近で育てられる瓜を玉造黒門越瓜と呼びました。
形は長く大きく、濃い緑に白い縞模様が入っています。
漬物を始め、多様な調理法で楽しむことが出来ます。
勝間南瓜(こつまなんきん)
ねっとりとして水分の多い、日本かぼちゃの一種です。大阪市西成区玉出(旧勝間村)の農家が江戸時代に扱っていた記録が残っています。
熟すと果皮がオレンジ色になり、甘みが増していきます。
天王寺蕪(てんのうじかぶら)
大阪市の天王寺付近が発祥とされ、特産物として様々な文献にも記述があります。
甘みが強く、緻密な肉質が特徴で、漬物や煮物に適しています。
田辺大根(たなべだいこん
現在の東住吉区の特産だった田辺大根は、ずんぐりとした円筒形の白首大根です。
昭和初期にウイルス病により一度姿を消しましたが、昭和62年の品評会にて再発見され、現在まで維持・保存されています。
肉質は緻密で柔らかく煮物にすると甘みがでます。
鳥飼茄子(とりかいなす)
鳥飼茄子は、京都の賀茂なすのようなソフトボール大の丸ナスの一種です。
摂津市の特産品として江戸時代から親しまれてきました。
皮が柔らかく、肉質は甘みがあり緻密なので、田楽や煮物、焼き物などに向いています。
三島独活(みしまうど)
江戸時代より茨木市三島地域で栽培されてきた独活。
現在では1軒のみの農家さんが三島独活を守り育てています。
アクが少なく香りは強く、色白でみずみずしいのが特徴です。
吹田慈姑(すいたくわい)
江戸時代以前から吹田市で自生していたクワイ。
中国産のものと比べて、小型でエグみが少なく、栗のようなホクホクとした甘さが感じられます。
YACYBERに掲載中の「平野農園」さんが中心となり、吹田くわいの伝統を守っています。
碓井豌豆(うすいえんどう)
羽曳野市碓井地区で育てられてきた碓井豌豆は、明治時代にアメリカから導入されたえんどう豆を改良したものです。
甘みが強く、淡い色と小型のサイズも特徴の一つです。
「なにわの伝統野菜」の今後
「伝統野菜」は、安定した生産・供給のために品種改良された野菜とは異なり、地域・季節・食べ方が限定されています。その性質から大量生産・大量消費は難しいですが、逆に上手くPRすることで地域や農家の振興には大きな役割を担うことが期待されています。
そのためには種を守り続けていく生産者、食べ方を提案する料理研究家や加工開発者、歴史的意義やその美味しさをPRする販売・流通業者など、分野の垣根を越えた連携が必要になってきます。
生産・加工・流通・販売・消費など、あらゆる人が手を取り合って地域の伝統を守り発展させていく、その媒体として「伝統野菜」は大きな可能性を秘めています。