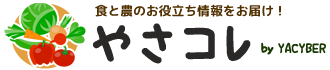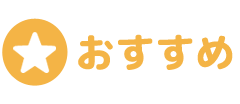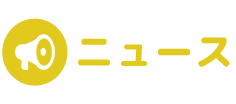「ただちゃ豆」
だだちゃ豆は、鶴岡周辺の限られた地域で江戸時代から農家が大切に守り生産されてきた枝豆の「在来種」です。
外皮が褐色がかり、表面のうぶ毛が茶色で、くびれも深いため見た目は良くありませんが、ゆで上がる頃にはとうもろこしのような甘い香りが漂い、
食べると甘みと旨みがどんどん口の中に広がり、食べ始めたらもうやめられなくなるほど。そのため「枝豆の王様」と呼ばれています。
栄養面でも、シジミを超えるオルニチンが入っており、肌の若返り効果のある成長ホルモンを分泌を促進し、美肌を守る効果があります。
しかし、だだちゃ豆は鶴岡の土地条件にマッチしており、同じ種子を他の地域で生産しても、その品種特性が消えてしまうという「わがまま」な枝豆です。
しかも少数の農家の方しか生産されていないため、地元の人もなかなか手に入れるのが難しく、「幻のだだちゃ豆」とも言われています。
だだちゃ豆農家の朝はとても早く、まだ夜が明けないうちから、ライトを照らして収獲作業がはじまります。
豆が活きているため、収獲して1時間も経つと豆が熱を持ち始めます。
しかし、枝豆は暑さに弱く、デリケートな農作物のため、農家では新鮮さを保つために、日の出前に収獲し、昼には発送の手はずを整えるようにされています。
このような努力のおかげで、美味しいただちゃ豆が食べられるのですね。
「だだちゃ」とは、庄内地方の方言で「おやじ」「お父さん」という意味。
その昔、城下町・鶴岡が庄内藩だった頃、枝豆好きな殿様が城下から毎日持ち寄らせては、
「今日はどこのだだちゃの枝豆か?」と聞いていたことから、だだちゃ豆と呼ばれるようになったとされています。
【美味しい茹で方】
- 洗い桶に豆を入れ、水を少なめに入れて、ゴシゴシ強くこすり毛を洗い流す。
- ザルに上げて、水気を切る。 鍋に豆の量の約3倍の水を入れ、塩を少々入れた後、沸騰させる。
- 沸騰した湯の中に豆を入れてふたをする。(約3~4分)
- すばやくザルにあけて、塩をふり、うちわなどで扇いでさます。
出回る時期:8月旧盆ごろ~9月上旬